パズル&ドラゴンズ
clear
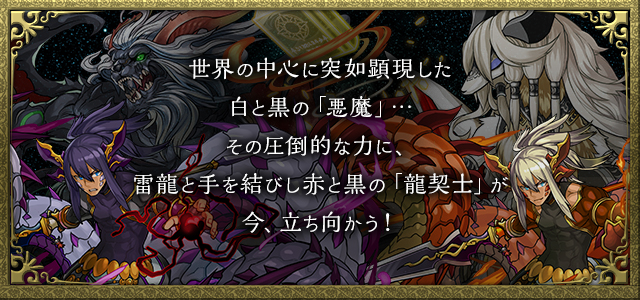
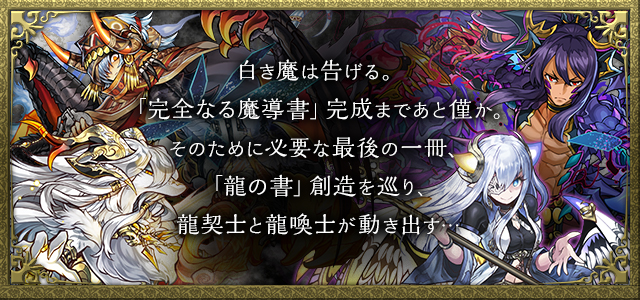
- [2025/07/08(火)更新]
- 最新5話を追加

絆の章【現状】

-
ヴァレリアの屋敷に身を寄せたティフォン達は、回復術の使える者から傷の治療を受け身体を休めていた。
「……」
「どうしたのシルヴィ、何か考え事?」
「いいえ、大したことではないの。ただ少し……クァージェと繋がってない自分に、戸惑っているだけ」
シルヴィの言葉で、リューネは彼女の背へと視線を向ける。
龍と契約し身体の一部にその力を発現していた”龍契士”達は、レーヴェンから受けた術の影響により、身体に大きな変化が現れている。
シルヴィが龍と繋がっていたことで発現していた大きな翼はなくなり、リューネがトアと繋がることで使えていた還爪も、ただの人の手になっていた。
「ったく面倒ったらねぇぜ。傷の治りが遅すぎる」
「それも、俺達がただの人に戻ったということなのだろう」
ガディウスのぼやきに、ティフォンは苦笑しながらもその事実を重く受け止めていた。
龍の力を失ったことで、回復力をはじめ、身体能力も人間に戻ってしまっている。
(ドルヴァの力が無ければ、こうも無力なのか)
さらに龍との契約で生命を維持していた者は、そのつながりを絶たれたことで再び瀕死の状態となっている。
龍との契約解除。たったそれだけで、ティフォン達は戦力のほとんどを奪われた。
(再び龍契士となるには、かけられた術を解く方法を見つけなければ)
じわり、握りしめた手に汗がにじむ。
そんな中、上層部へ事の次第を報告しに向かっていたヴァレリア、ニース、そしてリクウが、屋敷へと戻って来た。
「はぁぁ……二度と見たくないと思っていた顔ぶれが勢ぞろいでした……しんどい」
「何どんよりしてんだリクウ。そのクッソ長い髪バッサリさせてスッキリさせてやろうかー?」
「全力で遠慮します! 刀ちらつかせないでくださいスオウ殿! 今の僕はあなたに殴られてもすぐ再生しないんですからね!?」
「そりゃ残念なこった」
やれやれと肩をすくめる暴君にやや距離を置きながら、リクウはこほんと咳払いをして話を始める。
「……ひとまず、手に入れてきた情報をお伝えします。まず天城から消えたレーヴェンの行方ですが、彼は今『聖域』にいるようです」
聖域。そこはミルが守っていた、継界や転界、その他全ての界の狭間に存在する特別な空間だ。すべての狭間――つまり、全ての界につながる場所ということ。
レーヴェンはそこで魔導書の力を使うつもりなのだろうというのが、全員の見解だった。
「彼の目的は、全ての世界を一度滅ぼし”龍”のいない世界を再構築すること。龍喚士の長と龍王は、彼を今一度封印するために動くそうです」
その言葉にティフォンが眉を寄せる。
「俺達は……あの人が父だという実感がまだないから。だが、リクウは……」
彼はかつてレーヴェンの仲間だった。
本当にそれでいいのかと戸惑うティフォンに、リクウは苦笑いを浮かべて首を横に振る。
「心配無用です。それに僕も、彼をこのままにしておきたくないですから。再封印するという龍王達の決定に否を唱えるつもりはありません。……現状、それしか彼を止める方法もありませんからね」
本当は自分の手で親友を止められたならよかったが、今のリクウにその力はない。
それはこの場にいるほとんどの者も同じだった。
「あの時天城にいた連中がレーヴェンから受けた術については、まだ解呪の方法がわかってねぇ。だが膨大な術が折り重なって成立している複雑な術だ。どうにかほころびを見つけて、効果を弱めることはできるはずだぜ」
スオウは友人であるチュアンをこの場に呼び出していた。
希代の細工師。細工によってあらゆる効果を品物に付与することができる者。
彼女なら、召喚や契約を阻害している術の解析と、弱体化・解呪ができるかもしれない。
「……今は体を休めながら、それがうまくいくことを祈るしかないな」
「おそらく進軍には間に合わないでしょう。しかし今の僕達はどうしたって戦力外です。再び力を取り戻せるまでは、龍王たちに任せるしかありません」
「仕方ねぇか。とにかくさっさと力を取り戻して、加勢に行けるようにするしかねぇ。何もできないまま八方塞がりってわけじゃないだけマシだと思っておこうぜ」
ガディウスの言葉に、全員が静かに頷く。
ここまで深く関わり、力を尽くしたというのに、最後は前線に出ることが叶わないかもしれない。あの時天城で戦った誰もがその歯がゆさを感じながらも前を向く中、スオウは一人思案する。
(……それまで奴が大人しくしてりゃいいんだがな)
絆の章【影と闇】

-
「我が影よ」
全ての界の狭間、全ての界と繋がる『聖域』の中心で、静かな声がこだまする。
感情も温度もないその声に呼応するようにして、一つの影が蠢いた。
己の分身とも呼べるラジョアに、レーヴェンは手にしていた魔導書を掲げる。
「――全ては、龍無き世界の為に」
魔導書からあふれる力が、ラジョアの奥底にある”核”の中へと流れ込む。
膨大な力を受けた核は、影を際限なく生み出していった。
それはすぐに膨張し、はじけるようにしてラジョアの中から溢れ出す。
影が染み渡るようにして広がるその様を、レーヴェンはただ静かに見つめていた。
ティフォン達が今後の方針を相談してから、数日が経過した。
龍王達は再度レーヴェンを封じるべく、聖域へと進軍を開始している。
そこに自分がいないことへの焦りを覚えながらも、一刻も早く力を取り戻そうと各々できることを考えながら日々を過ごしていた。
そんな中。
「だめだね、こりゃワガハイの手には負えないよ」
術の解析・解除のために屋敷へ来ていたチュアンは、あっさりとその解除方法の模索に匙を投げた。
「イルミナとかいったかい? あの犬のお嬢ちゃんと一緒に調べてみたけどねぇ。とんでもなく精密な術式が何重にも混ざり合っているんだよ。よくもまぁ、こんな術を組み上げたもんさね。完全に解析して解除や弱体化させるとなると、年単位で時間がかかるよ」
「チュアン殿でも駄目なのか……」
「これはいよいよもって手だてがないの」
チュアンなら解除は無理でも、解決の糸口を見つけてくれるやもしれない。
そんな期待も水泡に帰し、見解を側で聞いていたニースとエンラはどうしたものかと頭を抱えた。
「龍の召喚も、龍との契約も、大元をたどれば龍との”繋がり”を得て行われるということはわかるね?」
「ああ。それが今は術によって絶たれているということだろう?」
「絶たれてしまったならば再び繋げば、おそらく召喚も契約も可能になるはずじゃ」
「そう。問題はその方法さねぇ」
通常の召喚や再契約は、レーヴェンの術の阻害で不可能となっている。
再び龍と繋がるためには別の方法を見つけることが必要だが、それは決して簡単なことではない。特に人と龍との契約は召喚と違い事例も少ない分、確立された知識や情報そのものが乏しいのだ。
「もっと何か、人と龍を”繋ぐ”手がかりがあれば……」
「繋ぐ……――そういえば」
ふと、何かを思い出したようにエンラが顔を上げる。
「イデアルが以前、”繋ぐ”力を込められた石を持っておったな」
「石……? それはどんな石だい? 何かの鉱物か、それもと魔力の結晶体か」
「妾も詳しくは聞いておらぬが、それを媒介にしてあの子は一時的に龍契士となったことがあるのじゃ」
「ああ、あの時のことか。確かその石の力と経験を元にして、イデアルは後に人為的に龍契士を生み出す禁術を……!?」
生み出した、そうニースが言い切る前に、ガシッと彼女の両肩をチュアンの豆だらけの手が引っ掴む。
「その石、今何処にある!?」
「え、た、確か今はイデアルの館にあるはずで……」
「それを! 今すぐ! ワガハイに調べさせてくれないかい!?」
「落ち着け細工師。館はマイネというイデアルの弟子が管理しておる。イデアルと小僧の状況も説明せねばと思っておったし丁度良い、マイネに石を持って此処へ来るよう頼むとしよう」
屋敷でさまざまな者たちが手だてを講じる中。
スオウは屋敷から少し離れた山の崖上で周囲を見渡しながら、嵐の前の静けさに眉をひそめていた。
「……」
「何か考え事か、スオウ」
いつの間に近くまで来ていたのか、ヴァレリアが不思議そうに声をかける。いつもの飄々とした雰囲気が珍しくなりを潜めているスオウを気にかけ、追いかけてきたようだ。
「この静けさがちっとな」
「ふむ。ならばユキアカネ殿の目を借りてみてはどうだ?」
言わんとしていることをすぐに理解したヴァレリアは、その真っすぐな視線を彼の隣に向けた。
今現在、ユキアカネとの契約は強制解除されており、当然スオウはこの状態で未来を視ることができない。だがそれは視界共有が途切れてしまったからであり、ユキアカネ自身が持つ全てを見通す瞳は健在だ。その目は過去を、現在を、未来を視ることができる。
名を呼ばれたユキアカネは、ゆっくりと伏せていた顔を上げスオウを見据える。
『契約なしに視界を貸すのは負担が大きい。ほんの少し先のことしか見られないが、それでも良いかい』
どこか心配を含んだ問いかけに、スオウはそっとユキアカネの顔へ手を伸ばす。
「大丈夫だ。ありがとな、ユキ。無理させちまって」
『……構わないさ、お前が望むのならね』
互いに額を合わせ、ゆっくりと両の目を閉じる。
ユキアカネは己の瞳で視る一番確率の高い未来を、スオウの脳裏に映し出した。
望んだ風景が瞳に映った瞬間、ドクンと心臓が大きく脈打つ。
『――これは』
「……――!?」
ひざ下から崩れるように体勢を崩したスオウを、慌ててヴァレリア支える。
覗き込んだその顔は、血の気が失せて真っ青になっていた。
「……やべぇ」
たった一言そうつぶやくと、スオウはユキアカネに飛び乗り一目散に空を駆ける。
「おい!? 一体何を視たんだ!?」
「最悪の未来だ!」
そう叫んだ彼には、いつもの余裕めいた気配はかけらもなかった。
――同刻。
聖域の入口では、龍王と龍喚士の長たちがレーヴェンを倒すべく進軍を進めていた。
彼等が聖域へ進行しようと、その領域に足を踏み入れる瞬間。
聖域を中心に巨大な影が発生する。
『……何だ?』
龍王たちが警戒する中、まるで闇のように深く暗い影が足元を覆ったその時。
『――!?』
言葉を発する暇もなく、龍王たちは影に飲み込まれてしまった。
影は次々に、継界全土に存在するありとあらゆる“龍”を取り込んでいく。
「トア!」
「クァージェ!?」
「フラグレム!!」
サリアたちの契約龍も。
『クーサマ……! クーサマ……!』
「……そう、始まりましたのね」
クーリアたちの龍さえも。
「どうにかなんねぇのかよ、セディン!」
『無茶言うな。こりゃどうしようもねぇ。それくらい強い術だぜ』
『かの者の力と意志は強い。――貴様はそれでも、願いを貫くことができるか。ティフォン』
「ドルヴァ……」
二対の雷竜すら、言葉だけを残し成す術なく影に飲み込まれていった。
影は聖域を中心にすさまじい速度で広がっていく。
空に逃げても、海に逃げても、影からは逃げられない。
すべての龍が等しく闇に取り込まれ、消えていく。
「どうなってんだよ、これ……!?」
「スオウ様……!」
その影は、ヴァレリアの屋敷でハイレンの手伝いをしていた二人の少年少女にも迫っていた。涙を浮かべて怯えるオメガを庇うように抱きしめながら、アルファは心の中で何度も助けを呼ぶ。
「アルファ、オメガ!」
その声に応えるかのように、二人の姿を見つけたスオウが駆け寄ってきた。
「スオウ!」
「スオウ様!」
安堵の表情を浮かべて、小さな手を伸ばす二人。その手を掴もうと、両手を伸ばした瞬間。
「――!?」
目の前で影に飲み込まれてしまった。
『――スオウ!』
「ユキ!?」
二人を襲った影は息つく間もなくユキアカネをも覆いつくす。
とっさにその影へ腕を突っ込むが、影はスオウを飲み込むことなく、地面に染み込むようにして消え去った。
しんと静寂を取り戻したその場所で、スオウのみが残される。
何も破壊せず、誰も傷つけず、ただ”龍”だけを飲み込んで消えた影。
(アルファも、オメガも――ユキアカネも、消えちまった)
――この瞬間。
継界全てを包み込んだ影により、継界からすべての"龍"が姿を消した。
絆の章【悪魔と獄幻魔】

-
聖域から広がった影により、すべての龍が姿を消してから数日。
継界はバランスを崩し、天変地異などの大きな異変が立て続けに起こるようになった。
地は割れ、緑は枯れ、空は常に雷雲が立ち込め雷の雨を降らせている。
大気に漂う魔力や自然の力も弱まり、生命力の弱い生き物から次々に倒れていった。
「魔導書の発動を、止められなかったのか」
「間に合わなかったってことかよ……!」
龍を失い、全員が絶望に消沈する。しかも、事態はこれで終わりではなかった。
「……この術は、まだ発動の途中です」
深刻な面持ちでそう告げたのは、術を分析していたリクウとイルミナだ。
「この術の発動は、まだ完了していない。不完全。なぜなら私たちの記憶や知識に“龍”という概念がまだ残っているから」
イルミナは淡々と説明していく。
本来レーヴェンの魔導書が完全に発動すれば、自分達の中から"龍"という概念そのものが消えているはずなのだ。
しかしまだティフォンたちは、己の契約龍や召喚龍のことを覚えていた。
龍という種族がいたということを記憶している。それはまだ術の発動が途中であるため。
「今はまだ龍たちの姿が消えただけにすぎません。しかし時間が立てば、僕達の中から"龍"に関する事柄や記憶が薄れていくでしょう」
そして最後は、龍という種族のすべてを忘れる。龍という存在が”なかったこと”になる。
「どうにかできないのかよ!?」
ガディウスの叫びに、リクウとイルミナはどちらも返す言葉がないまま口を噤む。
この二人でも、対抗策が見いだせなかったということだ。
「チュアンさんが調べていた”繋ぐ”力をもつという石も、彼女の龍が消えてしまったことで調査が頓挫したそうです」
イデアルの館からマイネに持って来させたその石は、再び龍と人を繋ぎ、再召喚・再契約を可能にすることができるかもしれないわずかな希望だった。
しかしどうやってその力が発動するのかわからないままでは、ただの道端の石と大差がない。唯一その力を行使したイデアルも、治療が難航しており、とても話ができるような状態ではなかった。
「スオウは……」
「……」
今までその目の力で幾多の未来を視、事前策を講じてきた彼ならば。
そんなティフォンの期待に、リクウが首を横に振る。
彼も大事な二人の子どもと共に、最愛の家族であったユキアカネを失っていた。
未来を見据える瞳はユキアカネのものだ。彼女をなくしたスオウの瞳は、ただの暗闇しか映せない。
「……どうにもできねぇってことかよ」
吐き捨てるようなガディウスの言葉。それが現実だった。
人だけの力ではどうすることもできない。
その場にいた全員が、己の無力と絶望を痛感する――そんな中。
「人の力でどうにもならないのであれば、人ならざる者が動くまで」
諦めを孕まない言葉とともに、破壊の幻魔が姿を見せた。
その隣には娘のロミアが、一歩後ろには配下のスカーレットとアーミルが控えている。
「我々はズオー様と共に聖域へ向かい、レーヴェンを打倒してまいります」
「僕達悪魔は、君達みたいな力の制限なんて受けていないからね。だから何の心配もいらないよ僕のマイハニー!」
「アーミル……」
「……ワオ。いつものツッコミが入らないなんて相当参ってるね、シルヴィ。君のそんな顔は見ていられないよ。僕がすぐ笑顔に変えてあげるから、安心して待っていてね」
こんな状況下でもいつも通りの軽口とウィンクを決めるアーミルに、シルヴィは無意識のうちに小さく苦笑する。
その側で、イルミナは不安げな面持ちのまま、ロミアの服の裾をそっと握った。
「……ロミアも行くの」
「はい。私もお父様の役に立ちたいですから。……大丈夫ですイルミナちゃん。お父様はとっても強いのです!」
不安げな親友を励ますように手を握って、力強い笑みを浮かべてみせる。
そんなロミアを見て、イルミナも覚悟を決めた。
「――私は、ここでレーヴェンの術を何とかする方法を見つける。本当は離れたくない、一緒に行きたい。でも……私もロミアみたいに、ちゃんと私ができることをしなくちゃ」
「イルミナちゃん……!」
「おやおやおや、可愛らしい友情ですねぇ、涙が出そうですねぇ! クスクスクスクス」
少女たちのやり取りを笑う声がその場中に広がる
全員が警戒心を露にする中、声の主はどろりとした黒泥の中から姿を現した。
「どうも皆様、天城での戦い以来ですねぇ。生きて再会できるとは嬉しいかぎりです。ケラケラケラケラ」
「貴様、何をしにここへ来た!?」
激昂するニースと、静かに怒りを募らせるリクウ。
二人の殺気を全身に浴び、それでもダンタリオンという悪魔は顔に張り付けた笑みを崩すことなく一礼してみせた。
「なぁに、私どもも獄幻魔さんにご協力しようかと思いましてねぇ」
その言葉を合図に、泥の中から多くの悪魔たちが姿を現す。
中にはダンタリオンに引けを取らない爵位持ちの悪魔の姿もあった。
この軍勢で、獄幻魔と共闘するというのだ。
「理解に苦しみます。貴方、ご自分がしたことをお忘れですか?」
「いえいえ、しっかり覚えていますとも。貴方のご友人がたを唆したことも、貴方のお仲間のご家族で人形劇に興じたことも、忘れるはずかないでしょう? どれも私にとって、とても楽しい喜劇だったのですからねぇ」
「――っ!!」
その一挙手一投足すべてが神経を逆なでし、二人の殺気を増幅させる。
これほど悪魔らしい悪魔もいないだろう。
ダンタリオンはケラケラ笑いながら、己の意図を開示する。
「貴方がたの絶望は充分味わいましたので、次は育ち切ったであろう彼の絶望を味わう頃合いかと思いましてね」
自身が面白いと判断した者へ手を貸し、耳元で甘言をささやき、心を煽り立てる。
そうして目の前で繰り広げられる阿鼻叫喚を堪能しつくし、飽いたら簡単に手を放す。
それが悪魔という存在だ。
今は予定通りに進むレーヴェンより、どうなるか分からない不安定なこちら側に手を貸すのが面白そうだと判断したらしい。
「とは言いましても、私どもが加わったところで、果たしてかの方にどれだけ対抗できるかわかりませんけれどねぇ。私どもがこちらに付くことなど、今やかの方にとっては憂慮すべきものではないでしょうから。生まれたての仔猫に、小さな牙が生えた程度にしかならないでしょうねぇ。クスクスクス」
笑いながら発せられた現実を、ズオーは否定しない。
破壊を司る魔物と、爵位持ちの悪魔の軍勢を集結させたとしても、レーヴェンを止めることは難しいのだ。その力を目の当たりにしたティフォン達は、両者の差をよく知っている。
「適わないとわかっているのに、行くのか」
その問いかけに、ズオーは少しばかり己の意思に火を灯すきっかけとなった男を見つめると、閉じられていた重々しく口を開く。
「力の差も、敗北の二文字も。それだけでは抗う事を……我が願いを諦める理由にはならない。その程度で諦められるならば、人が持つ願いなど所詮はその程度だったということだ」
たったそれだけを静かに、しかしはっきりと告げる。
「――貴様は、諦めることができるか?」
「……!」
その問いかけに対するティフォンの返答を待たず、ズオーは身を翻し他の者たちを引き連れて戦場へと赴いていった。
残されたティフォンは、投げかけられた言葉を心の内で反芻する。
(俺とて……諦めたいわけじゃない)
それでも現状、自分に力が無いことは変わらない。
諦めたくはない気持ちと、それでも手が届かない現実に苦悩する。
――しかし彼等には悩む時間すら与えられない。
継界全土に浸食した影は、急速に効力を強めていったのだ。
絆の章【忘却と願い】

-
ズオーたちが聖域へと向かった後。
屋敷に残された者たちは、そのほとんどが為す術なく待つだけだった。
それでも幾人かは、諦めずに打開策を模索し続けた。
しかしそんな者たちに追い打ちをかけるかのように、龍の存在を奪う影の力は増していく。
「リィ、大丈夫か」
屋敷の一室。ティフォンとラシオスは、小さな少女の様子を見にきていた。
「うん。リィ、大丈夫だよ」
ベッドに座りながら絵本を読んでいたリィは、元気そうに笑顔を見せる。
他の重傷者に比べてそこまで傷が深くなかった彼女は、他より早く意識を取り戻していた。
しかし目が覚めたと言っても傷を受けていることには変わりなく、加えて状況が状況なだけに部屋の外へ出すわけにもいかず。
結論として、リィは部屋の中で過ごしてもらうことになったのだ。
「お見舞いだ」
「わぁ、お花いっぱい! ありがとう、お兄ちゃん!」
ラシオスが摘んできた野花を、リィは満面の笑みを浮かべながら受け取った。
小さな両手には少し多かったのか。ぽろりと一輪こぼれ落ちたそれを拾い上げ、ティフォンがそっと髪に差してやる。
「えへへ、ありがとうお兄ちゃん!」
「どういたしまして」
そのままふわふわの髪をそっと撫でる。
くすぐったそうな、しかし嬉しそうにする少女を見て、ほっと安堵の息を吐いた。
「ひとりで退屈してはいないか」
「大丈夫だよ。お屋敷のみんなも、お姉ちゃんたちみたいにリィとお話してくれるから」
「そうか。それは嬉しいな」
「うんっ。貰ったお花で、こうやってかんむりも作ったりしてるの」
受け取った花の茎を編み込み、瞬く間に小さな花冠が出来上がる。
「綺麗にできているな」
「えへへ。リィ、これが一番上手にできるんだよ」
「すごいな、私は不器用だからこんなに綺麗には作れない。いつもはアイツが――…………」
ラシオスが、ぴたりと口の動きを止める。
「……ラシオス?」
「……アイツ、が……いつも……私の、代わりに……」
脳裏に浮かんだ戦友の名を呼ぼうとして喉から出かかったはずの名前が、頭の中で霧散する。
不器用な自分を仕方がないなと助けてくれた戦友。口下手が過ぎてすれ違いを起こし、敵となって再開し、再び絆を繋ぐことができた元相棒。
今まで忘れることなどなかったその存在の名前が、声が、姿が。
「――アイツのことが、思い出せない」
「……っ!?」
その一言で、ティフォンはラシオスに何が起きているのかに気が付いた。
呆然とした様子のままのラシオスに、何も知らないリィはきょとんと首をかしげながら、手元の花冠に視線を落とす。
淡い野花で編み込んだ、小さな小さな花冠。
「……あれ?」
ふと、リィの脳裏に誰かの照れくさそうな顔が浮かんだ。
その”誰か”の頭に、花冠をのせてあげたことを思い出す。しかし――……。
「リィ、この花冠……誰かにあげたのかな?」
リィは花冠を渡した”誰か”の名前を、思い出せなくなっていた。
(これが……存在が消えるということなのか)
この世界から “龍”の存在を消す術が、完全なものに近づいているという実感を、ティフォンはさまざまと感じさせられた。
それからティフォンは急いで屋敷内の仲間達に声をかけた。
自分の相棒を、契約した龍を、大事な戦友を、憎んでいた相手のことを覚えているかと。
しかしティフォンが期待した返事を、誰一人返してはくれなかった。
シルヴィは誰の側にいたかったのかを、キリは何を憎んでいたのかを。
クーリアは何を嫌っていたのかを、思い出せなくなっている。
「……”全ては龍なき世界のために”だったかしら。フフ、そう。いざ現実になってみると、こんな気持ちになるものなんですのね」
捕縛され屋敷の地下牢で行動を制限されていたクーリアは、まるで自嘲するように肩をすくめた。あれだけ毛嫌いしていた、自身のことを好いていた龍。
(本当に、いなくなってしまえばいいと思っていたはずですのに)
その願いに偽りはなかったはずのクーリアの顔は、まるで晴れやかなものではなかった。
状況を確認した後、ティフォンは屋敷から少し離れた丘の上で、混乱するばかりの頭を冷やしていた。
(皆、大なり小なり龍の記憶を失いつつあった……)
確認する限り、欠落の速度には多少の個人差があるようではあった。
姿は思い出せるのに名前がわからない者や、その逆。恨みや慈しみの気持ちは残っていても、その相手を思い浮かべようとすると、まるで霧に包まれたかのうように頭が働かなくなる者もいる。
しかし程度の差はあれど、皆一様に”龍”に関することを忘れかけているのだ。
龍と共に歩んだ者も、龍を憎んでいた者も。感情を向けていたその存在が、記憶が欠落していく。
(今もきっと、気づかないうちに記憶は消えている……)
ゾッと背に怖気が走る。己が気付かないうちに、頭の中を作り変えられているようなものだ。それは破壊の獣魔と戦った時より、父と相対した瞬間よりも、不安と恐れを感じさせる。
「……兄貴」
「――っ!?」
思考に浸かりきり、すぐ後ろまで近づいていた弟に呼ばれたことでハッと意識を浮上させる。
情けない姿を見せてしまったと慌てて振り向いたティフォンは、目に入ったガディウスの表情に、どうしかしたのかと喉まで出かかった言葉を思わず飲み込んだ。
「……」
声色はどこか弱く、常に前を見据えていた瞳の色は陰りを見せ、いつもの強気な様子はすっかりなりを潜めてしまっていた。
こんなガディウスの顔を見るのは初めてで、ティフォンは驚きを隠せない。
少しの間、互いの間に広がった静寂。それを破ったのは、ガディウスだった。
「サリアが……自分を育てた龍王の名前を思い出せなくなってやがった」
「……」
「他の奴らも似たような感じでよ。みんなどんどん、龍のことを忘れて……。しまいには、そいつとの思い出や大事だったはずの気持ちまで、忘れかけてやがる」
龍についての全てが記憶から抜け落ちる。最初からすべてが“なかったこと”になる。
それはつまり、龍に関わることで抱いた願いや想いすらも“なかったこと”になるということだ。
「俺も、少しずつセディンを忘れていく。このまま何もできなかったら……」
セディンと契約した理由も、何を願って契約したのかも、忘れてしまう。
「……故郷が獣魔たちに滅ぼされた時も、天城で暴走しちまった時も、こんなことは思わなかったのに」
ガディウスの瞳が、兄を映す。
「なあ兄貴。……オレ、初めて“怖い”って思ってる」
ティフォンは瞳を大きく見開いた。
元々気が強く負けん気で、契約者となり互いに剣を交え、共に戦い隣を任せられるほどに強くなった弟は、これまで弱音など一切吐かなかった。
そんなガディウスが初めて見せた不安に、ティフォンは拳を握りしめる。
(俺は、弟にこんな顔をさせない為に、龍契士になったんじゃないのか)
たった一人の弟を守るために、ティフォンはドルヴァと契約し戦いに身を投じた。
しかし龍が消え、ただの人間に戻り、その願いを叶えられるだけの力はもうない。
『――貴様は、諦めることができるか?』
あの時、ズオーに問われた言葉を思い出す。
(このまま何もできず、諦められるのか……)
目の前で不安に押しつぶされそうになっている弟を守れず、
己の願いを諦めることができるのか。
「――諦められるはずがなかったな」
「……兄貴?」
どこか呆れたように、しかしどこかすっきりしたような笑みを浮かべ、ティフォンはそっと、目の前の大切な弟に手を伸ばす。
「何も心配しなくていい。俺がなんとかしてみせる」
「なんとかって……」
「お前を守るために、俺は龍と……ドルヴァと契約したんだ」
その願いだけは、絶対に忘れない。
「俺は最後まで自分の願いを諦めない。その願いの為にドルヴァと契約したことも、これまで戦ってきたことも、全て忘れたりしない」
たとえ力を無くしても、己の願いを認めてくれたドルヴァがいなくなってしまったとしても。
「俺は俺の願いのために、最後まで足掻こう」
絆の章【信条と持てる全て】

-
レーヴェンが発動した術によって目の前でユキアカネやアルファとオメガを失ったスオウは、一人何をするでもなく、呆然と屋敷の中をふらりふらりと歩いていた。
(守れなかった……アイツらを、ユキを……)
どうしたらよかったのか、もう何をしても無駄なのか。
未来を見据える瞳は暗く閉ざされ、打つ手を考える時間すらもほとんど残されてはいない。
大事な家族を無くした喪失感と己の無力、絶望がスオウの心を押し潰していく。
(……もう、どうしようも)
そんな彼の後頭部を、何かが盛大にどつき倒した。
「あ~ごめんないさいっス荷物で前見えなくて……って、あれセンパイじゃないっスか。なに病室の前で突っ立ってるんスか」
「ハイレン……?」
高すぎず低すぎないニュートラルな声と自分を“センパイ”呼びする独特な口調で、今自分がいる場所がどこだったのかと、後頭部に一撃を与えた犯人を知る。
「とりあえず、そこどいてほしいっスー」
「あ、ああ……」
ハイレンはそのままサクサクと病室に入り、手にしていた包帯や薬といった備品の山を手早く仕分けていく。
イデアルやアルトゥラの為に看護を手伝っていたマイネにそれらの扱いを軽く説明し終わると、くるりと振り返って再びスオウに声をかけた。
「んで、センパイは病室に何か御用っスか? 見たトコ重傷重篤じゃなさそうっスから、急ぎじゃないなら後に回してほしいッスよ。自分、今から重傷者の治療始めるんで」
「治療って……お前、機龍の相棒いなくなっちまったんだろ」
レーヴェンの術によって、リヴァートも姿を消してしまっている。彼の最新鋭の技術サポートを無くしたことで治療に必要な電子機器が軒並み使えなくなり、持ち直しかけていたイデアルやアルトゥラといった重傷者の生命維持が困難になっていた。
「そっスね。でもそれがどうかしたんスか?」
「は……?」
しかしそんな最悪の状況を感じさせないような軽快な口調で、ハイレンは当然のように言ってみせる。
「相棒がいないのはそりゃ痛手っスよ。でも自分にやれることはまだあるっスから」
「いや……でもお前、この状況じゃ」
何をしたってもう。そう言いかけたスオウに、ハイレンは笑って己の心臓の上に手のひらを重ねる。
「あのですねセンパイ。どんな状況下でもやれることが残っているうちは、全力でそれをやりきってからじゃないと、医者は諦めることを許されないんスよ」
それはスオウでなく、自身に向けて言い聞かせているような言葉だった。
ハイレンはそのまま目を閉じ、すぅ、と静かに息を吸い込み、胸に重ねた手のひらに力を籠める。
そこからぽぅ、と淡い光があふれ出すと、光は瞬く間にハイレンの全身を包み込み、その背に大きな翼を発現させた。
「ハイレン、お前……」
四枚の翼と頭上で輝く円環。神々しい光を放つそれは、神界出身であるハイレン本来の姿だった。
ハイレンはこの姿を滅多にみせない。神の奇跡による治癒は強力な分、それに慣れてしまえば、人間が元来備えているはずの自然治癒力を衰えさせてしまうからだ。
奇跡に頼らず、医者として人の体がもつ生命力に寄り添い命を繋ぐ。それがハイレンの、医者としての信条のひとつ。……それでも。
『目の前に救うべき患者がいて、これ以外に方法がないのなら。信条など、いくらでも捨て去ります』
今ここに――神の奇跡を!
神々しい宣言と共に四枚の羽を大きく羽ばたかせ、ハイレンは病室全体に神術を行使する。
神の奇跡によって降り注ぐ治癒の光は、病室にいたイデアルやアルトゥラたちを包み込み、消えかけていた生命を再び灯した。
視界が暗闇に閉ざされたスオウも、その光の温かさを肌で感じ取る。
この光は、医者としてのハイレンがもつ“目の前の命を救う”という願いの現れだ。
信条を曲げてでも、願いのために持てる全てを尽くしている。
(オレは……こいつみたいに、自分の持てる全てを尽くしたか?)
やれることは、本当にもうないのか。
『患者の方々の命は、自分が繋ぎ留めます。貴方は、これからどうするのですか』
ハイレンの問いかけに、スオウは静かに顔を上げた。
罫線
※パズドラクロス・TVアニメーション等の設定とは異なります。

















